発見日 2021年4月6日

何回か撮ったが、中々写真ではうまく見えるように撮れない。
これでもベストショットだ。
旧町名由来案内

町の起立は明治五年(1872)である。対馬の宗家厳原藩と伊勢国の久居に陣屋を構えた久居藩の邸地そして周辺の武家地を合併して二長町とした。
町名はこの地が江戸時代より「二丁町」と呼ばれていたことに由来する。二長町とは、この地を東西に横切る小路につけられたとされているが、その由来はあきらかではない。この小路が東西に二丁あったからではないだろうか。
江戸時代は武家地であったため町名が付されてなく、町としての発展は二長町となった明治以降である。特に明治二十五年(1892)浅草猿若町から市村座がこの地に移転して来てから賑わい始め、二長町の名は東京中に知れ渡った。明治三十年代頃、東京郵便局厩舎課があり、市内に郵便物を輸送する赤塗りの馬車が発散集合していたことも「新撰東京名所図会」は述べている。
昭和三十九年(1964)住居表示の実施で、蔵前橋通りの南側が台東一丁目に、北側が同二丁目に編入された。
二長町小学校校歌

二長町小学校は、明治11年に開校した下谷練塀小学校を始まりとしている。
下谷練塀小学校は,大正12年の関東大震災により焼失し,当時の下谷区仲御徒町59番地(現在の台東区上野5丁目)から二長町2番地の2(現在の台東区台東1丁目)に移転した。
その後、昭和20年4月3日の空襲で校舎に被災。
昭和21年 御徒町小学校と統合。
昭和22年 学制改革により台東区立二長町小学校と改称。
平成2年 二長町小学校と竹町小学校が統合して台東区立平成小学校が開校。
二長町小学校は閉校となる。
二長町町会掲示板
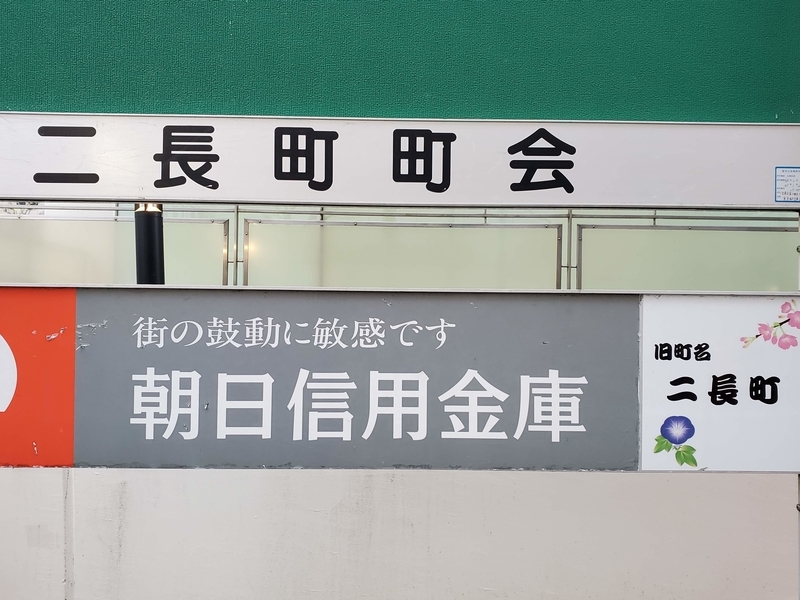

台東区ホームページより
台東区南西部 竹町地区の台東1丁目2丁目の東側にある町会です。
町会名の由来は、この地が江戸時代より「二丁目」と呼ばれていた事によります。
二長町交差点

発見日 2022年8月14日
発見場所 東京都台東区台東一丁目5
市村座跡


明治25年(1892)11月、下谷二長町1番地といったこの地に、市村座が開場した。市村座は歌舞伎劇場。寛永11年(1634)日本橋葺屋町に市村座は創始し、中村・森田(のち守田)座とともに、江戸三座と呼ばれた。天保13年(1842)浅草猿若町2丁目に移り、ついで当地に再転。
二長町時代の市村座は、明治26年(1893)2月焼失。明治27年(1894)7月再建して東京市村座と呼称。大正12年(1923)9月の関東大震災で焼けたが再興、昭和7年(1932)5月に自火焼失し消滅という変遷を経た。明治27年(1894)再建の劇場は煉瓦造り3階建で、その舞台では、六世尾上菊五郎・初代中村吉右衛門らの人気役者が上演した。岩百合菊五郎・吉右衛門の二長町時代を現出し、満都の人気を集めた。しかし、その面影を伝えるものはほとんどなく、この裏手に菊五郎・吉右衛門が信仰したという、千代田区稲荷社が現存する程度である。
平成6年3月
台東区教育委員会
2023年1月7日撮影
